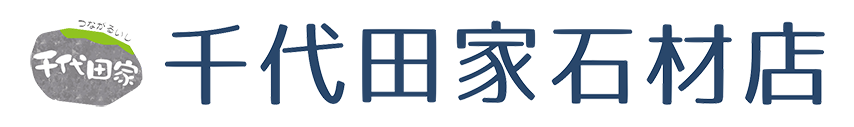八柱霊園 でのお墓・納骨・墓じまいなどを
お考えの方は千代田家 石材店 へご相談ください。
「八柱霊園での納骨、どこに頼めばいいのだろう…」と不安を抱えるご家族は少なくありません。
火葬を終えて埋葬許可証を受け取ったものの、納骨室を開けてご遺骨を納める作業はご自身で行うことはできません。
専門技術を持つ石材店が、墓石の開閉や納骨室の整備、当日の埋葬の流れを担います。
だからこそ、信頼できる業者選びが安心の供養につながります。
本記事では、八柱霊園で納骨を依頼する際に知っておきたい業者の選び方や費用感、当日の段取りを丁寧に解説。
初めてでも落ち着いて準備が進められるようサポートします。
目次
納骨・埋葬とは?基礎知識
身近な方が亡くなられたとき、火葬が終わった後に残るご遺骨をどのように扱うのか。
これはご家族にとって大きな関心事であり、同時に戸惑いの多い場面でもあります。
特に「納骨」と「埋葬」という言葉は日常生活ではあまり使うことがなく、同じ意味だと思われがちですが、実はそれぞれに異なる意味と役割があります。
ここでは、八柱霊園での手続きを考える前に押さえておきたい、基本的な知識について詳しく解説いたします。
「納骨」とは?
「納骨」とは、火葬を終えたご遺骨を骨壺に納め、それをお墓や納骨堂、合葬墓などの納骨施設に安置することを指します。
つまり「骨を納める行為」そのものを表す言葉です。
一般墓であれば、墓石の下にある納骨室(カロートと呼ばれるスペース)に骨壺を納める作業を行います。
八柱霊園では、この納骨作業を石材店が専門的に行うのが基本となっており、ご家族だけで行うことはできません。
納骨は単なる「作業」ではなく、ご家族にとっては大切な供養の儀式です。
多くの場合、僧侶や神職をお呼びして読経や祝詞をあげていただき、ご先祖様や新たに亡くなられた方の冥福を祈ります。
納骨をもって「お墓に入る」という意味合いが強まり、家族の心情としても一つの区切りを迎える瞬間になります。
「埋葬」とは?
一方、「埋葬」とは、ご遺骨を大地に埋めて供養することを指します。
法律上も「埋葬」とは、焼骨を墓地や納骨堂に収蔵することを広く含む概念とされています。
つまり、納骨という行為も広い意味では「埋葬」の一部といえるのです。
古来、日本では土葬が一般的でしたが、火葬が主流となった現代では「火葬後に骨壺を墓所に納める」という形が一般的な埋葬のあり方です。
八柱霊園でも同様に、火葬後に発行される「埋葬許可証」を提出して初めて納骨・埋葬が可能になります。
したがって、埋葬という言葉は法的な手続き全般を含む広い意味合いを持ち、納骨はその具体的な実施行為と理解すると分かりやすいでしょう。
八柱霊園における納骨・埋葬の位置づけ
八柱霊園は公営霊園であるため、納骨・埋葬の際には必ず埋葬許可証が必要となります。
火葬場で受け取った許可証を霊園の管理事務所に提出し、石材店にお骨を納めてもらうという流れです。
石材店は墓石の蓋を外し、納骨室を清掃し、ご遺骨を丁寧に安置します。
その後、再び蓋を閉じるまでを担当します。
この一連の作業が安全に行われるためには、専門的な知識と経験が欠かせません。
また、八柱霊園には一般墓、芝生墓地、合葬墓など様々な形式の墓所があり、納骨・埋葬の方法もそれぞれ異なります。
宗教的・文化的な意味合い
納骨や埋葬は単に法律や霊園のルールに基づいて行うだけでなく、宗教的・文化的にも深い意味があります。
仏教においては、故人が成仏するための大切な儀式のひとつとされ、納骨法要を営むことでご先祖様と故人の霊を手厚く供養します。
神道では「埋葬祭」として行われ、清めの儀式が重視されます。
キリスト教においては埋葬式が行われ、祈りとともに遺骨を墓所へ納めます。
宗教は異なっても「故人を安らかに送り届ける」という想いは共通しており、その象徴的な場面が納骨・埋葬なのです。
八柱霊園を利用する方々も多様な宗教背景を持っており、それぞれのご家族が大切にする形式で納骨・埋葬が執り行われています。
石材店はこうした文化的な背景にも配慮しながらサポートするため、依頼先選びはとても重要だといえるでしょう。
納骨・埋葬の心理的な役割
納骨や埋葬には、ご遺族にとって心理的な意味合いも大きくあります。
ご遺骨を自宅に一時的に安置する期間を経て、お墓に納めることで「本当にお別れした」という実感を得る方も少なくありません。
八柱霊園という落ち着いた環境の中で、自然に囲まれながらご遺骨を納める時間は、ご家族の心に静かな区切りを与え、これからの生活を支える力となっていきます。
このように、「納骨」と「埋葬」は似ているようでいて、それぞれに明確な意味と役割があります。
八柱霊園でお墓を持つ方にとって、納骨・埋葬は単なる手続きではなく、ご家族の心をつなぎ、世代を超えて続いていく供養の大切な節目となるのです。
八柱霊園での納骨の流れ
八柱霊園での納骨・埋葬は、多くのご家族にとって人生の中でも特に大切な節目となります。
だからこそ「どんな準備が必要なのか」「当日はどう進むのか」をあらかじめ知っておくことが安心につながります。
ここでは、八柱霊園での納骨の流れを、手配から当日の埋葬まで順を追って解説します。
事前準備と必要書類
まず、八柱霊園で納骨を行うために必要書類となるのが「使用許可証」と「埋葬許可証」です。
埋蔵施設 使用許可証
八柱霊園でお墓を利用する際に必ず必要となるのが「埋蔵施設 使用許可証」です。
これは、霊園の管理者である東京都(都立霊園としての八柱霊園の場合)が「この区画をあなたが使用できます」と正式に認めた証明書で、お墓の権利を示す大切な書類です。
使用許可証は、墓所の抽選や申込みに当選した後、所定の手続きを経て交付されます。
この証明書を持つことで、はじめて墓石の建立や納骨・埋葬が可能となります。
逆に言えば、この書類がなければ八柱霊園でお墓を建てることも、納骨を行うこともできません。
埋葬許可証
火葬場で火葬を終えた際に市区町村から発行されるもので、正式名称は「埋火葬許可証」といいます。
この書類がなければ、八柱霊園での納骨・埋葬はできません。
ご家族の中には「なくしてしまった」という方もいらっしゃいますが、その場合は役所で再発行が可能ですので、早めに確認しておきましょう。
お墓の使用者(名義人)の確認
次に確認すべきは、墓所の使用者(名義人)です。
八柱霊園のお墓を利用する場合、名義人が手続きを行うのが基本となります。
ご高齢や体調の都合で名義人が動けない場合には、別のご家族が代理を務めるケースもあります。
事前に石材店や霊園管理事務所に相談しておくとスムーズです。
また、納骨当日に必要な持ち物としては、骨壺・埋葬許可証・お供え(お花や果物など)・法要を営む場合はお布施などが挙げられます。
準備を整えておくことで、当日の慌ただしさを軽減できます。
石材店への依頼と打ち合わせ
八柱霊園では、納骨の実務作業は石材店が担当します。
墓石の蓋を開け、納骨室を整え、ご遺骨を収め、最後に蓋を閉める作業には専門技術が必要だからです。
そのため、納骨を希望する日程が決まったら、必ず石材店に連絡をして予約を入れましょう。
石材店との打ち合わせでは、以下のような点を確認しておくと安心です。
-
希望する日程と時間帯
-
法要を行うかどうか(僧侶を呼ぶ場合は、お寺との連絡も必要)
-
お花や供物の準備について
-
参列者数や当日の交通手段など
石材店はこれらを踏まえて、当日の段取りを整えてくれます。
経験豊富なスタッフが多いため「初めてで不安」という方でも安心して任せられます。
管理事務所での手続き
納骨当日には、まず八柱霊園の管理事務所で手続きを行います。
ここで必要になるのが「使用許可証」と「埋葬許可証」です。
八柱霊園の管理事務所に提出し、職員の確認を受けたうえで、正式に納骨が認められます。
この手続きは原則として名義人が行いますが、事前に石材店へ依頼してサポートを受けることも可能です。
霊園の規則は公営ならではの厳格さがあるため、書類不備がないように確認を怠らないことが大切です。
納骨当日の流れ
書類の確認が終わると、いよいよ納骨・埋葬の開始です。
一般的な流れは次のとおりです。
墓前に集合
石材店のスタッフが事前にお骨を収める準備を行い、墓前にてお待ちしております。
家族や親族が墓前に集まり、祭祀を執り行う方を呼ぶ場合も現地にてお待ち合わせを行います。
墓石の開閉
石材店が墓石の蓋を慎重に外し、納骨室を開けます。
場合によっては内部を清掃したり、新しい敷石を整えることもあります。
納骨(骨壺の安置)
骨壺を納骨室に安置します。
複数のご遺骨を同時に納める場合には配置の工夫が必要となるため、石材店が案内してくれます。
その後、花立や香炉を整えて読経や焼香へと移ります。
法要・焼香
僧侶の読経や焼香を行い、故人の冥福を祈ります。
宗教・宗派によっては儀式の形式が異なりますが、いずれも厳かに進められます。
墓地の整地
石材店が蓋を閉じ、墓所の整地を行います。
納骨後の流れと心構え
納骨が終わった後は、会食や簡単な親族の集まりを行うご家庭もあります。
ご遺族にとっては気持ちの区切りとなる大切な時間です。
納骨・埋葬は形式的な作業ではなく、ご家族にとって「故人を送り届ける大切な儀式」です。
八柱霊園のように自然豊かな環境で、石材店や僧侶のサポートを受けながら安心して執り行うことは、残された方々にとっても心の支えとなるでしょう。
このように、八柱霊園での納骨は「準備 → 石材店への依頼 → 管理事務所での手続き → 当日の納骨作業」という流れで進んでいきます。事前に必要書類を揃え、石材店としっかり連携を取ることで、当日は安心して大切な儀式に臨むことができます。
八柱霊園という歴史と自然に恵まれた環境で納骨を行うことは、ご家族にとって故人への想いを形にする大切な時間です。その一つひとつの流れを理解しておくことが、心穏やかな供養につながるのです。
納骨を依頼できる業者は?
八柱霊園で納骨や埋葬を行う際、多くのご家族が最初に迷うのが「誰に依頼すればよいのか」という点です。
火葬が終わり、ご遺骨を納める段階になると、納骨室を開閉し、骨壺を安置し、再び墓石を元に戻すという専門的な作業が必要になります。
では、実際に八柱霊園で納骨を担当するのは誰なのか。結論からいえば、それは「石材店」です。
八柱霊園では石材店が納骨を担当する
八柱霊園は公営霊園であり、園内の墓所に関する工事や納骨の作業は、霊園と契約している石材店が行う仕組みになっています。納骨を「自分たちだけで」行うことは基本的にできません。なぜなら、墓石や納骨室の構造は専門的であり、誤って扱えば破損の恐れもありますし、安全面でもリスクがあるからです。
石材店は墓石の施工・修繕だけでなく、納骨という儀式においても重要な役割を果たしています。ご遺族の立会いのもと、確実かつ丁寧に納骨を進めてくれるため、安心して依頼できるのです。
石材店に依頼するメリット
納骨を石材店に依頼するメリットは多岐にわたります。
-
専門的な技術と知識
墓石や納骨室の構造は複雑で、素人が扱うには危険が伴います。石材店なら専用の道具と経験豊富な職人が対応するため、確実で安心です。 -
スムーズな段取り
納骨に必要な書類や手続き、霊園管理事務所とのやり取りにも慣れているため、当日の流れがスムーズになります。「何を準備すればいいの?」と迷うこともなく、サポートを受けられます。 -
法要との連携
多くのご家庭では納骨と合わせて僧侶を招き、読経や焼香を行います。石材店はこうした法要の進行を考慮しながら準備を整えてくれるため、安心して儀式に集中できます。 -
アフターサポート
納骨当日の作業だけでなく、その後の墓石メンテナンスや修繕についても相談できるのは大きな利点です。お墓を長期的に守っていく上で、信頼できる石材店との関係は欠かせません。
選び方と注意点
八柱霊園には複数の指定石材店があり、利用者はその中から選ぶことができます。選ぶ際のポイントは以下の通りです。
-
実績や経験が豊富であるか
-
納骨や埋葬に関する説明が丁寧でわかりやすいか
-
見積もりが明確で、追加費用が発生しないか
-
法要や準備物の相談にも親身に応じてくれるか
納骨は人生の大切な節目ですから、信頼できる石材店を選ぶことが重要です。事前に複数の石材店に相談し、比較検討するのもよい方法でしょう。
八柱霊園で石材店に依頼する流れ
実際に依頼する場合の流れをまとめると、次のようになります。
-
日程の決定
葬儀や四十九日などの法要に合わせて納骨日を決めます。 -
石材店に連絡
希望日時を伝え、作業の予約を行います。 -
打ち合わせ
当日の段取りや必要な持ち物、費用の確認をします。 -
当日
石材店が墓前で準備・作業を行い、納骨をサポートします。
八柱霊園での納骨や埋葬は、石材店が担う重要な役割によって支えられています。
経験と知識を持つ専門業者が作業を担当するため、ご家族は安心して大切な儀式を迎えることができます。
納骨は単なる作業ではなく、故人を偲び、ご家族が心を一つにする大切な時間です。
そのひとときを円滑に、そして心穏やかに進めるために、信頼できる石材店の存在は欠かせません。
石材店に依頼する際の注意点
八柱霊園での納骨や埋葬は、石材店に依頼して行うのが一般的です。
しかし「ただお願いすれば大丈夫」と思ってしまうと、当日になって慌ただしい思いをしたり、想定外の費用がかかったりすることもあります。
ここでは、石材店に納骨を依頼する際に注意すべき大切なポイントを整理しておきましょう。
早めの予約を心がける
納骨は四十九日や一周忌など、法要の日程に合わせて行うことが多く、ご家族や親戚の方たちが集まりやすいように土日祝日に集中することがあります。
特に八柱霊園のように利用者が多い霊園では、春秋のお彼岸やお盆の時期は予約が混み合いやすい傾向にあります。
石材店も同時期に複数の依頼を受けているため、直前の依頼では希望日時に対応できないこともあります。
そのため、納骨日が決まり次第、できるだけ早めに石材店へ連絡して予約を入れることが大切です。
余裕を持った日程調整を行えば、法要を営む僧侶や親族の予定、法要後の会食も合わせやすくなります。
費用を事前に確認しておく
納骨にかかる費用は、石材店ごとに料金体系が異なります。
一般的には3万円程度が目安ですが、墓石の種類や納骨の方法によって追加費用が発生する場合もあります。
例えば、墓石の蓋が特殊な構造になっている場合や、複数の骨壺を同時に納める場合などです。
見積もりを取る際には、「基本料金に含まれる内容」と「別途費用が発生する可能性のある作業」をしっかり確認しておきましょう。
中には「納骨作業費のみ」なのか「簡単な清掃や片付けも含まれる」のかで差が出ることもあります。
当日の持ち物を確認する
納骨当日に必要となる主な持ち物は以下の通りです。
骨壺(分骨がある場合は複数)
埋蔵 使用許可証
埋葬許可証
お数珠
お供え(花・果物・お菓子など)
これらはご家族が用意するものと、石材店に依頼をして準備をしてもらえるものがあります。
「埋蔵 使用許可証」と「埋葬許可証」を忘れてしまうと納骨をすることは可能ですが、「八柱霊園にご遺骨を収めた」という記録が残らなくなってしまいますので、前日までに確認しておくと安心です。
法要の有無を明確にする
納骨の際に僧侶を招いて法要を行うかどうかも、事前に決めておく必要があります。
法要を行う場合は、石材店は僧侶の進行に合わせて納骨の段取りを組み立ててくれます。
一方で法要を省略し、納骨のみを行うご家庭も増えてきました。
どちらを選ぶかはご家族の考え方次第ですが、石材店に伝えておくことで当日の流れがスムーズになります。
また、法要を行う場合には読経の時間も含めて全体の所要時間を見積もっておくと安心です。
雨天や荒天時の対応を確認しておく
屋外で行う納骨は天候の影響を受けやすいものです。
そのため、あらかじめ「荒天の場合は日程を変更するのか」「小雨程度であれば決行するのか」を確認しておくと安心です。
石材店との信頼関係を築く
納骨は一度きりの作業ではありません。
将来的には追加の納骨、墓石の修繕、清掃、さらには改葬や永代供養墓への移行など、多様な相談が必要になることもあります。
信頼できる石材店を選び、日頃からコミュニケーションを取っておくことで、いざというときに頼りになる存在となります。
八柱霊園での納骨を石材店に依頼する際には、予約のタイミングや費用の確認、持ち物や法要の有無など、いくつかの注意点があります。
これらを事前に把握して準備しておくことで、当日は安心して儀式に臨むことができます。
納骨は故人をお墓に迎え、ご家族が心を込めて送り届ける大切な時間です。
そのひとときを円滑に進めるためには、信頼できる石材店に依頼し、しっかりとした準備を整えることが何より重要だといえるでしょう。
八柱霊園での納骨にかかる費用
八柱霊園で納骨を行う際、ご家族が気になることの一つが「どのくらいの費用がかかるのか」という点です。
お墓にご遺骨を納めることは大切な儀式であり、心を込めて準備したいものですが、同時に現実的な金額面も事前に把握しておきたいところでしょう。
ここでは、八柱霊園での納骨に関わる主な費用を大きく分けて解説していきます。
石材店への納骨作業費
納骨そのものの作業は、石材店に依頼することが一般的です。
墓石の蓋を開け、納骨室を整え、ご遺骨を安置し、蓋を閉じるまでを石材店が担当します。
この「納骨作業費」は、一般的に 1件あたり3万円~5万円前後 が相場といわれています。
金額の幅がある理由としては、墓石の形状や納骨室の構造、作業の難易度などが挙げられます。
例えば、古い墓石で重い蓋を外す必要がある場合や、内部の修繕・清掃を伴う場合には、追加費用がかかることもあります。
また、複数の骨壺を一度に納める場合や、粉骨をして収蔵スペースを確保する場合も、追加料金が必要になるケースがあります。
石材店によって費用の内訳が異なるため、事前に見積もりを取り「基本料金に含まれる内容」と「追加費用が発生する条件」を確認しておくことが大切です。
また、追加彫刻といって、亡くなられた方の情報(戒名・お名前・死亡年月日・年齢)を彫刻する場合は、別途費用が発生いたします。
法要にかかる費用(お布施など)
多くのご家庭では、納骨とあわせて僧侶を招いて法要を営みます。
この場合にかかるのが「お布施」です。
宗派や地域によって相場は異なりますが、 3万円~5万円程度 が一般的です。
加えて、僧侶が霊園に来る際の「お車代」や「御膳料(会食を用意しない場合の代替)」などを包むのが慣習です。
例えば、
-
お布施:3万円〜5万円
-
お車代:5千円〜1万円
-
御膳料:5千円〜1万円
といった形で、合計すると 4万円〜7万円程度 を用意される方が多いです。
もちろん宗派や菩提寺との関係によって金額は上下しますので、あらかじめ確認しておくと安心です。
お供えや準備にかかる費用
納骨当日には、お花や果物、お菓子などのお供え物を用意することがあります。
花束や供花は3,000円〜5,000円程度、果物や菓子折りも同程度の金額で準備される方が多いです。
また、納骨後に親族で会食を行う場合には、その費用も見込んでおく必要があります。
会食は近隣の料亭やレストランで行うケースが多く、1人あたり3,000円〜5,000円程度が目安です。
参列者が多い場合は、全体で数万円〜十数万円の費用になることもあります。
総額の目安
以上を合計すると、八柱霊園での納骨にかかる総費用は次のようなイメージになります。
石材店作業費:2万円〜5万円
僧侶へのお布施・お車代など:4万円〜7万円
お供え・会食費用:数千円〜十数万円(人数による)
合計すると おおよそ7万円〜15万円前後 が一つの目安といえます。
もちろん、法要を簡素化したり、会食を省略するなどご家庭の判断によって調整が可能です。
八柱霊園での納骨にかかる費用は、石材店への依頼費用を中心に、僧侶へのお布施や供花・会食などを含めて 7万円〜15万円程度 が一般的です。
金額には幅がありますが、事前に石材店へ相談し、見積もりを取っておくことで安心して準備ができます。
納骨は故人を偲ぶ大切な儀式です。金額だけでなく、ご家族の想いを大切にしながら準備を進めていくことが、心穏やかな供養につながるでしょう。
納骨当日の流れ
八柱霊園での納骨当日は、ご家族にとって大切な節目の一日です。
故人をご先祖様と同じ墓所にお迎えし、心を込めて供養するこの時間は、ご遺族の心に深く刻まれるものとなります。
しかし、初めて納骨を経験する方にとっては「何時にどこへ行けばいいのか」「当日はどんな段取りになるのか」と、不安も少なくありません。
ここでは、八柱霊園での納骨当日の流れを時系列に沿って丁寧に解説していきます。
集合
納骨当日は、まずご家族や親族が八柱霊園の墓所前、もしくは霊園入口や管理事務所付近に集合します。
参列者が多い場合は、事前に「集合場所」を決めておくとスムーズです。
近隣の石材店で納骨を依頼している場合、石材店の店舗を集合場所や休憩場所として利用することが可能となります。
八柱霊園は広大な敷地ではありますが、日差しや雨風を凌げる場所、座って休憩をする場所がありません。
地元の石材店を利用することによって、ご納骨式前後の厳粛な時間を過ごすことができます。
霊園管理事務所での手続き
八柱霊園の管理事務所で「埋蔵施設 使用許可証」と「埋葬許可証」を提出します。
こちらの手続きは、納骨の前後どちらに行っても問題はありません。
職員による確認が済むと、正式に納骨が認められます。
この手続きは原則として墓所使用者(名義人)が行いますが、体調や都合によって代理人が行う場合もあります。
事前に石材店での打ち合わせをされているのであれば、管理事務所でのやり取りや必要事項の確認をサポートしてくれます。
納骨室への安置と読経
手続きが済んだら墓前に移動し、納骨の準備が始まります。
準備がひと段落すると、石材店のスタッフが墓石の蓋を開け、ご遺骨を納骨室に安置します。
複数の骨壺を納める場合や、既に先祖代々のご遺骨が納められている場合には、配置の工夫が必要になるため、石材店が案内してくれます。
ご家族が迷うことなく納骨できるようサポートしてくれるので安心です。
ご遺骨を納め終えると、石材店が墓石の蓋を閉め、もとの状態に戻します。
この工程は慎重に行われ、最後に花立や香炉を整え、墓前をきれいに仕上げます。
僧侶を招いて法要を行う場合は、この時点で読経が始まります。
ご家族や参列者は焼香を行い、故人の冥福を祈ります。
法要を省略する場合でも、墓前で黙祷を捧げたり、お花を手向けることで心を込めたお見送りができます。
形式にとらわれすぎず、故人を偲ぶお気持ちが何より大切です。
納骨後のひととき
納骨が終わったあとは、墓前で写真を撮影するご家族も多くいらっしゃいます。
「この日、この瞬間をしっかり残しておきたい」というお気持ちからであり、後日思い返した際の大切な記録にもなります。
また、納骨を終えたあとに親族で会食を設けるケースもあります。
近隣の飲食店や仕出しを利用し、故人を偲ぶ語らいの時間を持つことが、ご家族の心を癒す大切な機会となります。
所要時間の目安
八柱霊園での納骨にかかる所要時間は、
-
管理事務所での手続き:約15分
-
墓前での準備・読経・納骨:約30〜60分
-
全体の流れ:約1時間〜1時間半
が一般的です。
ただし、参列者の人数や法要の有無によって前後します。
余裕を持ってスケジュールを組むことをおすすめします。
納骨は単なる作業ではなく、ご家族の絆を深め、故人を心に刻む大切な儀式です。
八柱霊園という自然豊かな環境の中で、心を込めて執り行うことで、ご遺族の心にも安らぎが訪れることでしょう。
八柱霊園での納骨に関するよくある質問
八柱霊園で納骨や埋葬を予定されている方の多くは、初めての経験で不安や疑問を抱えています。
ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ一つひとつ解説していきます。
事前に理解しておけば、当日を落ち着いて迎えることができるでしょう。
Q1. 八柱霊園で納骨できるのは平日だけですか?
A. 土日や祝日でも納骨は可能です。
ただし、霊園の管理事務所は年末年始など一部休業日がありますので、その期間は手続きができません。
また、土日祝日は利用者が集中しやすく、石材店や僧侶の予定も埋まりやすいため、早めのご予約が必要です。
特にお彼岸やお盆の時期は混雑するため、1〜2か月前から相談しておくと安心です。
Q2. 雨天でも納骨できますか?
A. 基本的には納骨は行われます。
ただし、台風や大雨など荒天の場合には、安全面を考慮して延期されることもあります。
石材店によっては「小雨決行、荒天時は延期」といった基準を設けていることが多いので、事前に確認しておきましょう。
納骨はご家族にとって大切な儀式ですから、無理をせず落ち着いて行える環境で執り行うことが大切です。
Q3. 複数のご遺骨を一度に納骨できますか?
A. 可能です。
一回の作業で複数の骨壺を安置することができます。
ただし、すでにご先祖様のご遺骨が複数納められている場合、スペースが足りなくなることもあります。
その際には、骨壺を小さなサイズに移し替える「粉骨」という方法をとることもあります。
どのように納めるかは石材店が提案してくれるため、事前に相談しておくと安心です。
Q4. 納骨を自分たちで行うことはできますか?
A. ご家族だけで納骨作業を行うことはとても困難な作業となります。
墓石の蓋の開閉や納骨室への安置は、専門的な技術と道具を持つ石材店が担当します。
専門の職人が作業をすることをお勧めする理由は、破損や事故を防ぐためです。
また、確かな知識を持った者が行わないと、作業内容が煩雑な場合は今後の墓所管理にも悪影響を及ぼしてしまうことがあります。
必ず専門のスタッフが常駐しているとこへの依頼をお勧めいたします。
Q5. 合葬墓での納骨もできますか?
A. 八柱霊園には一般墓だけでなく、合葬式墓所(合葬墓)も整備されています。
合葬墓では個別の区画を持たず、他の方々とご遺骨を一緒に埋葬する形になります。
永代にわたり霊園が供養してくれるため、承継者がいない方や、将来お墓の管理が不安な方に選ばれています。
一般墓での納骨と流れは異なるため、詳細は霊園事務所や石材店に確認するとよいでしょう。
Q6. 納骨の際に服装の決まりはありますか?
A. 特別な決まりはありませんが、法要を行う場合は喪服または黒や紺など落ち着いた服装が望ましいです。
カジュアルすぎる服装は避け、供養の場にふさわしい装いを心がけましょう。
お子様が参列する場合には、制服やシンプルな服装でも問題ありません。
Q7. 八柱霊園の駐車場は利用できますか?
A. 八柱霊園には決まった駐車場はありません。
八柱霊園を車で利用する場合は、園内の墓所の近くの道路に駐車をすることが可能です。
公共交通機関でのアクセスも便利なため、電車やバスを利用する方も少なくありません。
八柱霊園で安心して納骨するために
八柱霊園は、首都圏有数の規模を誇る公営霊園として、多くの方々に利用され続けています。
桜や紅葉に彩られる自然豊かな環境の中で、故人を偲び、ご先祖様を供養できることは、ご家族にとって大きな安心となるでしょう。
しかし、いざ「納骨」や「埋葬」を行おうとすると、必要な準備や手続きの流れに戸惑う方も少なくありません。
ここまでの内容を振り返ると、八柱霊園での納骨には大きく分けて以下の流れがあります。
事前準備と必要書類の確認
納骨の手続きを行う上で必要な書類は「埋蔵施設 使用許可証」と「埋葬許可証」です。
埋蔵施設 使用許可証は、墓所の抽選や申込みに当選した後や、承継をして名義変更をした際などに東京都より交付されます。
もし紛失をしてしまった場合は、事前に八柱霊園の管理事務所へ相談をするようにしましょう。
埋葬許可証は、火葬後に市区町村から発行されるこの書類がなければ納骨はできません。
紛失した場合には役所で再発行が可能ですが、余裕を持って準備しておくことが安心につながります。
石材店への依頼
八柱霊園では石材店が納骨作業を担当します。
墓石の蓋を開け、納骨室に骨壺を安置し、再び閉めるという一連の作業は専門技術を要するため、ご家族だけでは行えません。
信頼できる石材店に依頼し、事前に日程や費用、必要な準備について打ち合わせを行いましょう。
管理事務所での手続き
納骨当日には、管理事務所で埋葬許可証を提出する必要があります。
納骨当日の流れ
石材店が納骨作業を進め、その後墓前にて僧侶の読経やご家族の焼香を行います。
複数のご遺骨を一度に納める場合や、既にご先祖様がいらっしゃる場合は、骨壺の配置に工夫が必要になるため、石材店の案内に従うと安心です。
費用感
八柱霊園での納骨費用は、石材店への依頼料として3万〜5万円程度が一般的です。
また、追加彫刻といって、亡くなられた方の情報(戒名・お名前・死亡年月日・年齢)を彫刻する場合は、別途費用が発生いたします。
これに加えて僧侶へのお布施(3万〜5万円程度)、お供えや会食などを含めると、全体で7万〜15万円前後が目安となります。
事前に見積もりを取り、余裕を持った準備を行いましょう。
八柱霊園で納骨を安心して行うために
納骨は、単なる手続きや作業ではありません。
故人を正式にお墓へお迎えし、ご家族が心を込めて送り届ける大切な儀式です。
そのために大切なのは、 「正しい準備」 と 「信頼できる依頼先」 の二つです。
事前に必要書類や持ち物を揃え、石材店としっかり打ち合わせを行っておけば、当日は落ち着いて儀式に臨むことができます。
また、僧侶をお呼びして法要を営むかどうか、参列者の人数や服装なども含め、ご家族の考えを共有しておくことが大切です。
ご家族にとっての「心の区切り」
納骨や埋葬は、ご遺族にとって心の整理をつける大切な機会でもあります。
火葬を終えてからの期間はまだ悲しみが癒えきらないことも多いですが、八柱霊園という自然豊かな環境で静かにご遺骨を納めることで、「しっかりと送り届けられた」という安堵感を得ることができます。
納骨を終えた後、多くのご家族は「これでようやく一区切りついた」と語られます。
それは決して終わりではなく、ご先祖様と故人を大切に思い続ける新たな始まりでもあります。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。
実家が石材店のため、幼い頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。
大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。
多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。
終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
いのちの積み木/認定 ファシリテーター
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 終活協議会/終活ガイド 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
有限会社 松戸ペット霊園/メモリアルアドバイザー
お問合わせ
【和モダンスタイル 認定優良石材店】
【プペルメモリアル 正規販売特約店】
【みちのく銘石 正規認定取扱店】
【八柱霊園石材同業組合 会員】
有限会社 千代田家石材店
住所:〒270-2253 千葉県松戸市7-450(八柱霊園 中参道)
営業時間:8:00〜19:00(土日祝日営業)
店舗定休日:火曜(祝日・お盆・お彼岸・年末年始を除く)
※各霊園のご案内は随時行っております。
TEL/FAX:047-387-2929/047-389-0088
HP:https://chiyodaya.co.jp/
【パートナーシップ】